AIの技術が日々更新されている一方で、我々栄養士の仕事が奪われるのではないかという不安がある方も多いのではないでしょうか。
この記事では栄養士の仕事が栄養士に奪われない3つの理由を解説していきます。
AIは柔軟な対応ができない
そもそも栄養士はただ栄養食事療法を行うのではなく、その人に合った食生活の改善をしなければいけません。AIは与えられたデータや情報処理をするのは得意ですが、クライアント自身が上手く食習慣や生活環境、嗜好、心理的な問題をAIに出力しないといけません。また、その情報のニュアンスによっては誤った処理をする可能性があります。ある程度知識のある人が都合のいいように出力してしまうと全く違った食事療法の提案になることだってあります。言いにくいことや本音は信頼関係の中で生まれます。これは人間にしかできないことです。
AIは合理的で人間は非合理的
AIに提示してもらった答えは合理的です。その通りにやれば上手くいくことが多いと思います。ただ、人間は正しい行動ばかりを選択することができません。これは行動経済学でも示されています。プロスペクト理論に代表される心理バイアスが影響し、損失回避、現状維持バイアス、確証バイアスなどが合理的な判断を妨げます。感情や直感に影響されるため、正しいとわかっていても行動できないのです。
AIには個人の価値観を感じ取れない
AIの回答は過去のデータより蓄積された情報をもとに計算され導き出されています。そのため、大多数の人に当てはまるような事案でも個人に落とし込むと外れることも多くあります。わかりやすく言うとスクリーニングの時点でもう治療方針を判断してしまっている状態にあります。これは幅が広すぎてあまり良い策だとは言えません。個人の状況を正確に聞き取り、その人自身に合った治療を考える必要があります。
【番外編】AIに聞いてはいけないこと
法律に関することや最新のガイドラインなど
AIは最新情報や出来事に関する正しい回答を持っておらず、古い情報から抽出されたものを回答する可能性があります。これらに関しては各機関のホームページなどで直接確認する方が確実です。
個人を特定してしまうような情報
これはネットを活用すること全般に言えることですが、プライバシーの侵害や安全面から名前や住所、電話番号などは入れないようにしてください。AIはオンラインです。これを忘れないようにして下さい。
まとめ
AIは管理栄養士の代わりにはなれない一方で今後、管理栄養士がより活躍するためにはAIの活用が必須になるのではないかと思います。なぜなら、AIの登場がパソコンの登場とよく似ているからです。電卓を打ち栄養価を計算して、手書きで紙に献立作成をしていた時代はパソコンの登場によって大きく変化しました。今回のAIの登場によって栄養士は新たなツールを手にすることとなります。今、現場で活躍している栄養士でパソコンスキルが高い人は業務効率が高いはずです。これからAIを学ぶことは定型業務の効率化により生産性を高め、より良い栄養管理が行える未来がもうすぐそこまで見えています。AIの登場は管理栄養士にとって業務負担軽減とともにより患者様に寄り添えるパートナの登場だと考えていいと思います。
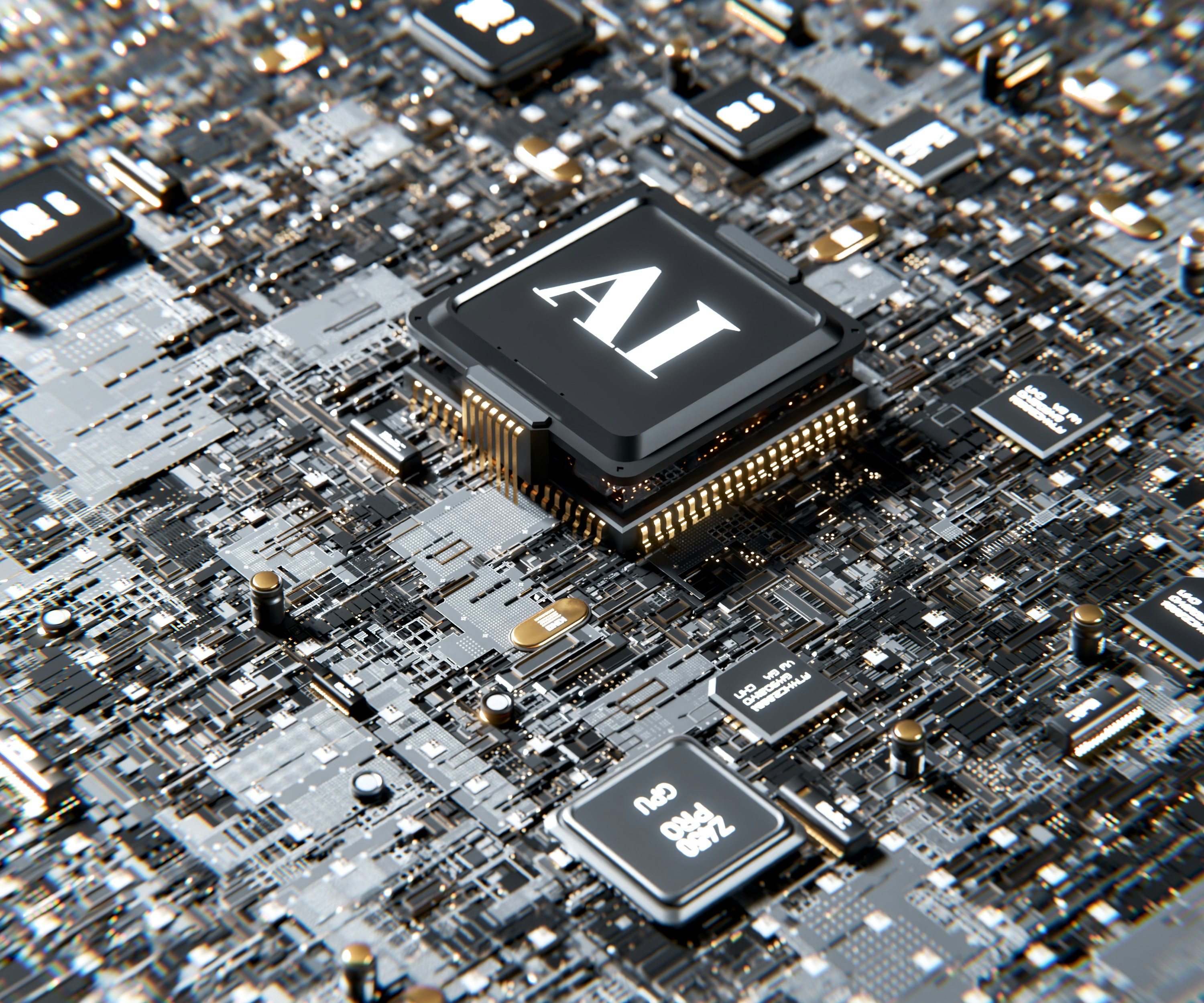
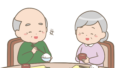

コメント